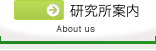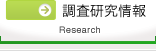�z�[��>���v���Ə��>2022�N�x�V���|�W�E��
�V���|�W�E��
2022�N�x�@�V�X�e���Ȋw�������V���|�W�E��
�n��Ƌ����ł���T�C�N���c�[���Y���ɂ͉����K�v���H
��ÁF��ʎВc�@�l�V�X�e���Ȋw������
 �@�u���]�Ԋ��p���i�@�v�i����29�N5��1���{�s�j�̂��ƁA�S���e�n�Ŏ��]�ԗ��p�̑��i��}�邽�߂̗l�X�Ȏ��g�݂��i�߂��Ă��܂��B�ߋE���ɂ����Ă��A�i�V���i���T�C�N�����[�g�Ɏw�肳��Ă��鎠�ꌧ�̃r���C�`���͂��߁A�e�n�ŃT�C�N�����O���[�g���ݒ肳��A�����n��̊�������ڎw�������g�݂��s���Ă��܂��B�������Ȃ���A�T�C�N���c�[���Y���ɂ��n�抈�����𐬌������邽�߂ɂ́A�n��𑖍s����T�C�N���X�g�Ƃ��̎M�ƂȂ�n�悪���݂��𗝉����A�����ł�����ƊW����z�����Ƃ��d�v�ł��B�����Ŗ{�V���|�W�E���ł́A���ꌧ�ł̃r���C�`�̎���������Ȃ���A���s����z�������ł̉ۑ���A�T�C�N���X�g�Ɠ��H���p�҂��������ׂ����X�N�ƃ}�l�W�����g���A�T�C�N���c�[���Y���ɌW�����X�ɂƂ��Ď��Ȃ���g�݂ւ̃q���g�ƂȂ�b�����Ă܂���܂��B
�@�u���]�Ԋ��p���i�@�v�i����29�N5��1���{�s�j�̂��ƁA�S���e�n�Ŏ��]�ԗ��p�̑��i��}�邽�߂̗l�X�Ȏ��g�݂��i�߂��Ă��܂��B�ߋE���ɂ����Ă��A�i�V���i���T�C�N�����[�g�Ɏw�肳��Ă��鎠�ꌧ�̃r���C�`���͂��߁A�e�n�ŃT�C�N�����O���[�g���ݒ肳��A�����n��̊�������ڎw�������g�݂��s���Ă��܂��B�������Ȃ���A�T�C�N���c�[���Y���ɂ��n�抈�����𐬌������邽�߂ɂ́A�n��𑖍s����T�C�N���X�g�Ƃ��̎M�ƂȂ�n�悪���݂��𗝉����A�����ł�����ƊW����z�����Ƃ��d�v�ł��B�����Ŗ{�V���|�W�E���ł́A���ꌧ�ł̃r���C�`�̎���������Ȃ���A���s����z�������ł̉ۑ���A�T�C�N���X�g�Ɠ��H���p�҂��������ׂ����X�N�ƃ}�l�W�����g���A�T�C�N���c�[���Y���ɌW�����X�ɂƂ��Ď��Ȃ���g�݂ւ̃q���g�ƂȂ�b�����Ă܂���܂��B
| �V���|�W�E��web���J | �ߘa5�N3��31���i���j�����J�@�@�Q����E������@���� |
|---|
| �@�@�u���T | ��ʎ�i�Ƃ��Ă̎��]�ԂƃT�C�N���c�[���Y�� �|���]�Ԓʍs�������̉ۑ�_�́H�| �u�t �F ���� �\�� �� �����ّ�w ���H�w�����s�s�H�w�� ���� 1998�N3�������H�Ƒ�w��w�@���H�w�����Ȕ��m����ے��C����A��w�H�w���y�؍H�w�ȓs�s�H�w�u������A�u�t�A�����ّ�w���H�w�����V�X�e���H�w�ȍu�t�A�y�������o��2017�N4�����A�����ّ�w���H�w���s�s�V�X�e���H�w�ȁA���݂͊��s�s�H�w�Ȃ̋����ɏA�C�B��U�́A��ʍH�w�E��ʌv��ŁA���Ɏ��]�Ԃ���ʂ̑��s�����⓹�H��Ԑ����A�����Ԍ�ʂ̏a�ؑ�Ȃǂ��e�[�}�Ƃ��Ă���B |
�i�N���b�N�ōĐ��B�_�u���N���b�N��YouTube�̃y�[�W�Ɉړ����܂��B�j |
|---|---|---|
 |
||
| �@�@�u���U | �r���C�`�̎��g�݂��猩����T�C�N���c�[���Y���̉ۑ�ɂ��� �u�t �F ���X�� �a�V �� ����v���X�E�T�C�N�����i���c��@�c�[���Y�����[�L���O���� ���ꌧ����w�A����w�@���o�āA��B�H�Ƒ�w��w�@���m����ے��P�ʎ擾�����ފw�B�͐��Ԃɂ�����Z���s���A�q���������Ă������Ƃ���A2009�N��Â���E�܂��Â���R���T���^���g���F�Ɂi�������傭����j�N�ƁB���ł���Z���s���A�q�̗��ꂩ��A���]�ԗ��p���i�ɋƖ��Ŋւ��悤�ɂȂ�B �ւ̍��т�ΐ��i���c��i���ԁj�̐ݗ��Ɩ���S�����A�ݗ������玖���ǒ��B����̎��]�Ԋ��p���i�̊����A�g�c�̂ł��鎠��v���X�E�T�C�N�����i���c��ɂ��A���ƂȂ����v�������莞����ւ���Ă���B |
�i�N���b�N�ōĐ��B�_�u���N���b�N��YouTube�̃y�[�W�Ɉړ����܂��B�j |
 |
||
| �@�@�u���V | �T�C�N���c�[���Y���ɂ����郊�X�N�ƕK�v�ȃ}�l�W�����g �u�t �F ���� ���l �� ������ЃX�}�[�g�R�[�`���O��\ ���{�T�C�N�����O�K�C�h������F�}�X�^�[�K�C�h �����̈��w��w�@�̈�w�C�m�ے��C����A���]�ԋ��Z�̃I�����s�b�N�I�肩���ʂ̃A�X���[�g�܂ŕ��L���g���[�j���O�w���B2013�N�A�v���E�R�[�`�Ƃ��ēƗ����A������ЃX�}�[�g�E�R�[�`���O��n�݁B ���̑��A�T�C�N���Z�C�t�e�B���s�ψ����A�T�C�N���X�N�[���Z���A�c�[���E�h�E���k�I�t�B�V�����A���o�T�_�[�AGIRO�A���o�T�_�[�AMAVIC�A���o�T�_�[�AXAZTLAN�A���o�T�_�[�������߁A���]�Ԉ��S���s�̃R�[�`���O��X�N�}�l�W�����g��ʂ��āA�T�C�N���X�|�[�c���C�t�̐U���ɐs�͂��Ă���B |
�i�N���b�N�ōĐ��B�_�u���N���b�N��YouTube�̃y�[�W�Ɉړ����܂��B�j |
 |
||
| �p�l���f�B�X �J�b�V���� |
�e�[�} �n��Ƃ̋�����ڎw���T�C�N���c�[���Y���̒z���� �p�l���X�g�i���s���j ���X�� �a�V �� ���� ���l �� �R�[�f�B�l�[�^�[ ���� �\�� �� |
�i�N���b�N�ōĐ��B�_�u���N���b�N��YouTube�̃y�[�W�Ɉړ����܂��B�j |
�V���|�W�E���̓���������������������ɃA���P�[�g�����肢���Ă��܂��B
�����͂�����������͂����炩�炨�肢�������܂��@�@���@�������N���b�N
[�ߋ��J�Õ��̍u���^���q��z�z���Ă���܂��B]
����]�̕���PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���A���莖�������L���̏�AFAX�ɂĂ��\�����݂��������B
��ʎВc�@�l�V�X�e���Ȋw�������i�������jFAX:075�|231�|4407
�����q�̗����͖����ł����A�����ɂ��Ă͂��q�l�̂����S�ł��肢���܂��B
![]() PDF�`���̃f�[�^���������������ɂ�
PDF�`���̃f�[�^���������������ɂ�
Adobe Systems Inc. (�A�h�r�V�X�e���Y�Ёj�� Adobe(R) Reader ���K�v�ł��B