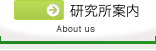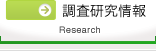ホーム>公益事業情報>米谷・佐佐木基金>過去の授賞式>第6回米谷・佐佐木基金
米谷・佐佐木基金
第6回 米谷・佐佐木基金授賞式
日時:平成22年11月26日(金)15:00〜17:00
場所:平安会館〜羽衣〜(京都市上京区烏丸通上町者町上ル)
| 一、開会の辞↓ | 近藤勝直 |
|---|---|
| 一、選考の経過並びに結果発表↓ | 藤原章正 |
| 一、受賞者の表彰↓ | 近藤勝直、佐佐木眞知子 |
| 一、受賞者(研究部門)の挨拶 | 羽藤英二 |
| 一、受賞者(学位論文部門)の挨拶と受賞講演 | 力石 真 |
| 一、閉会の挨拶↓ | 飯田恭敬 |
開会の辞
 |
本来ならば審査委員長の飯田恭敬先生からご挨拶申し上げるべきところですが、所用がございまして後ほどお見えになりますので、開会のご挨拶は私からさせていただきます。 今回で米谷・佐佐木賞も第6回となりましたが、だんだん認知をいただいて、定着してきたと考えています。 今後この米谷・佐佐木賞をさらに広く周知徹底していく必要があろうかと思いますが、その最大の理由は、研究部門では、50歳未満という年齢制限、それから交通工学と限定をしている関係上、だんだん母集団が減ってきてもう顔が見える状態に今はなっていると思います。 しかし応募者を増やすために交通工学以外の分野にまで拡げると、自動的に学位論文部門も拡がっていきます。現在学位論文部門は10名弱ぐらいの応募ですが、これが20名近くになったら我々審査員はギブアップしてしまいます。拡大したいけれどもジレンマも同時に抱えているということで、なかなか難しいことがございます。何かいいアイデアがございましたら、ご提案いただいたらありがたいと思っております。 本日の受賞者については溝上章志先生からご紹介がありますので、このあたりでご挨拶としたいと思います。ありがとうございました。 |
|---|
選考の経過並びに結果発表
 |
選考委員会を代表しまして、私から選考の内容についてご報告させていただきます。 米谷・佐佐木賞には研究部門と学位論文部門がございます。研究部門は50歳未満、49歳までの方に受賞の権利がある賞です。すでに評価の高い研究成果を残しておられるだけではなくて、現在斬新な研究プロジェクトを推進中、あるいは計画中であることが認められる研究者および技術者に授与される賞です。 今回は、プローブパーソン調査その他さまざまのデジタル的な道具あるいは方法を使い、交通行動をこれまでとは異なる方法で収集・分析し、それを実際に社会に実装していくことを積極的に行われている東京大学の羽藤英二准教授に決まりました。今後はいろいろな種類のデータをフュージョンして、彼はフュージョン・データと言っていますが、そのデータを利用した新たな交通行動モデルの構築を目指しておられるようで、その達成が期待されるところでございます。 一方、学位論文部門ですが、これは学位を取得されて3年以内の方に授与することになっています。今回は、大学の研究者だけではなくて、社会人ドクターなどで学位を取得された民間の方からも多くの応募をいただきました。 そのなかで、交通行動が内在している各種の変動を段階的に捉えてそれを統一的にモデル化する方法を提案され、その有効性を実際のデータを使って検証された、広島大学特任助教の力石真さんに決まりました。 できるだけ多くの方に応募していただいて、慎重・厳格にかつ合理的な審査を行うために、今回から二段階で審査をすることといたしました。第一段階では、簡易なプロポーザルを出していただいて、我々はどういう研究がされているかという目配りはできていますので、そのなかからこの人かなという数人を決めて、第二段階ではより詳細な資料を提出していただくという方法で今回は審査を行いました。 審査のために最初からたくさんのプロポーザルを書いていただくのは、応募者にとっても非常にロードが大きいということがわかってきましたので、今回からそのようにさせていただきました。今回初めてやったわけですが、このやり方で非常によかったと思っておりますし、まさしく米谷・佐佐木賞の趣旨にふさわしいご両名を選ぶことができたということで、審査委員全員が納得できた審査となりました。 お二人の今後のご研究のますますの成就を期待して、選考経過ならびに結果の発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 |
|---|
受賞者
研究部門
受賞対象既に評価の高い研究成果を発表するとともに、現在斬新な研究プロジェクトを推進中の若手の研究者あるいは技術者
 |
羽藤 英二 【 研究題目 】 |
|---|
学位論文部門
受賞対象 2007年4月から2010年9月に取得した特に優れた学位論文
 |
|---|
閉会の挨拶
 |
本日はお忙しいなか、米谷・佐佐木賞の授賞式にご出席いただきましてありがとうございました。 今回決まりましたお二人の方々については、交通現象の変動、動的変化、そういったものを分析する新しい方法論を考案されて、それが評価されたものと理解をしております。 私自身は前々から、交通現象というのは本来変動するものであって、平均値であるとか確定値であるとか、そういった値で交通の計画をする、あるいは交通の施設整備の評価をすることに関しては限界があり、問題があるのではないかなと思っています。お二人の発表は、そういった問題点を将来に向けて解決できる方向に示唆をいただける内容ではなかったかと思っております。 交通工学の分野は、国土交通省の予算が大幅にカットされて、事業費はもちろん研究費の面でも非常に厳しい状況にあります。さらに大学の状況を見ていますと、若い方がたの研究環境が極めて悪くなっている。具体的に申しますと、これまでのようにパーマネントではなくてテンタティブな任期制のポストで、腰を落ち着けて研究を進めるということがなかなか難しい状況になっています。 米谷・佐佐木賞がこういった状況下で、50歳以下の研究者、とくに若い学位論文をとられた方の支援に少しでもお役にたてればと願っております。事務局に聞きますと財源はまだしばらくは大丈夫だということですので、これからもささやかですが、こういった研究支援の事業を進めていきたいと思っています。 簡単ですがこれで閉会の挨拶に換えさせていただきます。どうもありがとうございました。 |
|---|