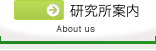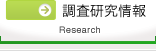ホーム>公益事業情報>米谷・佐佐木基金>過去の授賞式>第3回米谷・佐佐木基金> 受賞者(学位論文部門)の挨拶と受賞講演
米谷・佐佐木基金
受賞者(学位論文部門)の挨拶と受賞講演
 |
円山 琢也 【 研究題目 】 円山琢也と申します。この度は米谷・佐佐木賞学位論文部門をいただき大変光栄に思っております。現在、私は、アメリカのテキサス大学オースティン校というところで、日本学術振興会から、海外特別研究員としての支援をいただきながら、客員研究員として、武者修行をしております。はためからは、かっこよい肩書きに見えるかもしれませんが、中身は、任期付のポスドクということで、実際のところ、精神的にも、経済的にも苦労しながら生活をしております。そんな折に、いただいたこの賞は、私自身、大変励みになり、とてもありがたく感じております。 それでは、まず始めに学位論文の内容を簡単にご紹介したいと思います。 |
|---|
1.ネットワーク均衡モデルを応用した都市圏レベルの交通政策分析
|
(1) 背景・目的・貢献 研究の貢献としては、最適ロードプライシングあるいは最適職住配置を問題の対象にしてネットワーク均衡モデルの理論的拡張を行ったこと、さらに実際の大都市圏においてモデルの実用化を試みて実証的な貢献をしていることが、一つの特徴と言えるのではないかと思います。さらにモデルを用いた政策分析では、誘発交通を考慮した道路整備投資の評価であるとか、ロードプライシングの所得逆進性の問題点等々について検討を行っています。 |
|---|
|
(2) 学位論文の構成 以上が簡単にまとめた(簡単すぎるかもしれませんが)学位論文の内容ですが、本日はせっかくの機会ですので学位論文後の研究成果を少しご報告して、アピールをしたいと思います。 |
|---|
2.学位論文後の研究成果
|
2.1 ロードプライシング政策の比較分析 −コードン課金 vs エリア課金− ロードプライシング政策としては、コードン課金とエリア課金の二つが代表的な施策ですが、コードン課金についてはいろんな研究がなされているのに対し、エリア課金を厳密に評価した研究は今までにはありませんでした。そこでエリア課金を厳密に評価するための新しいモデルを構築し、それを実際の都市圏に適用してこの二つの課金の特性について比較検討しました。 (1) コードン課金とエリア課金の違い もう一つの図のように、複雑な移動をする場合ですと、コードン課金の場合では3回課金されますが、エリア課金の場合では一旦課金がされた後には課金されないというような違いがあります。コードン課金の場合には3回も課金されてしまいますので、例えば図の最後のトリップについては課金を避けるために経路変更をするといった行動変化が起きますが、エリア課金の場合ではそういったことは起きない、といった違いがあります。 |
|---|---|
 |
(2) モデリング上の問題点と解決策 一方、エリア課金では、利用者は1日単位で課金を支払う/支払わない の選択を行って、一旦支払った後では自由に走行が可能という関係になりますので、課金抵抗をリンク単位で表現するのはなかなか難しいことになります。これについて,いろいろ考えた結果、1日単位のトリップ・チェインの概念を利用すれば、エリア課金についても、利用者は1日のトリップ・チェインあたり最大1回支払うというように整理できるということがわかりました。トリップ・チェイン型のネットワーク均衡の拡張モデルというものを新しく考えると、コードン課金はリンク加法型のトリップ・チェイン・コスト、エリア課金はリンク非加法型のトリップ・チェイン・コストで表現することができます。 |
 |
(3) コードン課金とエリア課金の比較 (沖縄ネットワーク) 左のグラフは課金収入を比較したものですが、最適課金時の課金収入を比較しますと、最適エリア課金時の課金収入は、最適コードン課金時の課金収入の約1.6倍になっているということがわかりました。 (4) エリア課金とコードン課金の特性差 |
 |
2.2 交通需要のレベル別便益指標の一致性 (1) 交通投資の利用者便益評価 |
|
|
(2) 2つの便益指標 こういった構造を考えるとそれぞれの交通需要に応じて便益指標が定義できます。トリップ発生レベルの便益指標は一番上の式、ODレベルの便益指標は中ほどの式、リンクレベルの交通量の便益指標は一番下の式というように表現できます。そして、便益指標を積分で表現した場合には、実はこの全ての式は等しい、数学的には等価であることを、まず厳密に証明いたしました。一方、実際にこの便益指標を計算する場合には、台形公式を用いて積分を直線近似して求めることになりますが、台形公式で便益を定義した場合には、交通需要のレベル別便益指標は一般には一致しないということも示しました。 まとめますと、交通需要のレベル別の便益指標は、もし厳密に積分値で考えるのであればどのレベルでも一致することを理論的に証明しました。これは言われてみればあたりまえのことですけれども、今までこれを明示的に考えた研究はありませんでした。今回はネスティッド・ロジットモデルの場合をご説明しましたが、任意のランダム効用モデル、ワードロップモデルのような完全代替モデル、ODレベルの需要関数を考えたモデルでも成立することも網羅的に数学的に証明しています。また積分値では一致するけれども、台形公式を使って計算した場合には、レベル別の便益指標は一般には一致しないことも示したというわけです。 この点については実際に大規模ネットワーク上でも実証的に確認しましたが、その確認過程でわかったことは、リンク/経路レベルで便益を評価する場合は、一般的に積分の近似誤差が大きくなる傾向があるということです。したがって実際に便益評価を行う場合には、リンク/経路レベルではなくてODレベルで便益を定義するのが望ましいということを示しまた。したがって、この研究成果によって、私なりに先ほど述べた学術的な論争に対して明確な答えを出せたのではないかと考えております。 以上、学位論文の内容とその後に行った研究成果の報告を簡単にいたしました。今後もこの賞をいただいたことを励みにして、独立した研究者として攻めの姿勢を失わずにがんばっていきたいと思います。今後とも皆様からのご指導のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 |