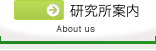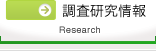�z�[��>���v���Ə��>�ĒJ�E�����؊��>�ߋ��̎���>��13��ĒJ�E�����؊��>�����u��
�ĒJ�E�����؊��
�����u��
 |
�J���@�� �y ������� �z �@���炽�߂܂��āA���̏܂����������܂��āA���肪�Ƃ��������܂��B�ߓ������搶�A�I�l�ψ��̐搶���A�����؍j�搶�̉��l�A�V�X�e���Ȋw�������݂̂Ȃ��܁A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B |
|---|
�͂��߂�
|
�@���������܂Ƃ����̂́A������Ă��܂��Ƃ���ŏI��邱�Ƃ������̂ł����A�{�܂́A�P�N�ԕ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃł����B����͂����ւ肪�������Ƃ������̂ł����A���������Y�݂܂����B�ꉞ�����2000�N���炢���猤�����Ă������ƂȂ̂ŁA��N�x���\�����Ă����������̂�15�N�����炢�ł����A���N���\���镪���P�N���ł͍�N�ƒނ荇�����Ƃ�Ȃ��B���Ƃ����ē����b�͐�ɂ������Ȃ��Ƃ������Ƃ������āA���낢��Y�̂ł����A�����̂̃f�[�^���@��N�����Ȃ���A�Ⴄ�l�������ł��邱�Ƃ�����̂ł��낢���荬���Ĕ��\�����Ă��������܂��B |
|---|
�\��
|
�@�ŏ��ɏ����������K�ł��B������������N�Əd�����܂��B�^�C�g�������ł��Ɖ��̂��Ƃ��킩��Ȃ��Ƃ��������Ǝv���܂����A���̘b�ł͓�������Ȃǂ͂܂������o�Ă��܂���̂ŁA�y�ȋC�����ŕ����Ă���������Ǝv���܂��B |
|---|
�y�����������K�z�@WAY�v��
|
�@�ŏ��͕��K�ł��B����͍�N���g�����X���C�h�ŁA�uWAY�v�ƕt�����t���A�ǂ�ǂ�ς���Ă��Ă���Ƃ������Ƃł��B��ʕ���ŏd�v�������̂́A�̂͂��Ƃ��C�M���X���ƁA�����͉^�͂ł���Ă����BWater Way�������킯�ł����A���ꂪ�Y�Ɗv����Rail Way�ɂȂ��āA����ɂ�Motor Way�ɕς��킯�ł��B���܂͌Œ�d�b���Ȃ��Ă�Cyber Way�ł��낢��ȂƂ���ɂȂ����Ă��܂��̂ŁA��ʍs�������{�I�ɕς���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ������������ۂɕς���Ă��܂����A�����Ă���Ƃ������Ƃł��B |
|---|
��ԏ�Ǎ����̃v���Z�X
|
�@���̂Ȃ��ŁA�����Ԃ��Ȃ�����͓k�����ł����ړ����ł��Ȃ������킯�ł����A���ꂪ�����Ԏ���ɂȂ莩���Ԍ�ʌ��ɂȂ��āA�x�O�ɃV���b�s���O�Z���^�[���ł��āA�s�S�����Ă��܂��B���A���y��ʏȂȂǂʼn����ł��Ă��邩�Ƃ����ƁA�u���n�K�����v������܂��傤�v�A�u�R���p�N�g�Ȃ܂��Â�������܂��傤�v�Ƃ������ƂŁA���̃X�P�[���œs�S�ƍx�O�Ƃ����܂����a���悤�Ƃ����l���������s���Ă��Ȃ��킯�ł����AIT����ɂȂ��Ă���ƁA�ȒP�Ɏ����Ԃōs����͈͂��щz���Ă��܂��āA���낢��ȂƂ���Ɍ�ʍs�����u��������Ă��܂��Ƃ������Ƃ��N����킯�ł��B |
|---|
�P���ѓ�����P�����Ԃ̃l�b�g�V���b�s���O�̎x�o���z�̐���
|
�@���ۖ��Ƃ��āA�����Ȃ���l�b�g�V���b�s���O�̃f�[�^�������Ă���ƁA���������T�N�Ŕ{�ɂȂ��Ă���Ƃ����X�����o�Ă��܂��B���炭�O�A�_�����o���n�߂�����́u���ɑ���Ȃ���肾�v�Ƃ����R�����g���Ԃ��Ă��Ę_���𗎂Ƃ��ꂽ�肵�Ă����̂ł����A�ŋ߂͂������ɂ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B���Ȃ�̊������l�b�g�ɃV�t�g���Ă��Ă���Ƃ������Ƃł��B |
|---|
���ԗ�F����҂̔������s���i���R��w���̃P�[�X�j
|
�@�������A���ꂪ�ǂ��ɍs���Ă���̂��Ƃ������Ƃ��傫�ȋ^��ł��B����͌������X�^�[�g��������ł����A���͑O�C�n�Ƃ��ĉ��R��w�ɂ��܂����̂ŁA���̎��Ƃ��Ă���w���Ʉ������̕i�������Ƃ����̂̓|�C���g�ɂȂ�̂ł����A�u�ޏ��ł��������Ƒ��ł������̂ŁA���̑O�v���[���g�����Ƃ��̂��Ƃ��v���o���āA����͂ǂ��Ŕ����܂������v�ƕ����܂����B �@��������ƁA���R��w�̊w���Ȃ̂ŁA�����������R�s�̒��S�s�X�n�Ŕ����Ă���B��ォ�痈�Ă���w�����L�����痈�Ă���w�����A�܂��Ȃ��Ŕ����Ă���B�ނ�����̂܂܃R���s���[�^�E���[���ɘA��čs���āA���������l�b�g�ŒT���Ĕ������O�Ŏ~�߂����܂��B�ǂ̂悤�ȃT�C�g���Ƃ��������������܂����A���̃T�C�g�̏��ݒn�ׂ�Ɠ����������ł��ˁB�֓���������Ɖߔ����ł��B�C�O�ɍs���Ă���҂����܂����A���ǂ͉��R�s���ɍs���Ă���҂͈�l�����Ȃ��킯�ł��B�s���悪�܂������ς���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��N���邱�ƂɂȂ�܂��B |
|---|
�l�b�g�V���b�s���O���p�̐��ݗv��
|
�@���ۖ��Ƃ��āA�l�b�g�ł��̂��Ă���l�͈���������̐l�Ȃ̂��B���������C���[�W���ŏ��͂����āA�܂��Ȃ��ɏo��l�ƈ���������̐l�Ƃ͂���ʂȂ̂ł͂Ȃ����Ƃ����������ŁA����������̐l���ǂ������炢���̂��Ƃ����c�_���ꎞ���i�݂܂����B���������ۖ��Ƃ��Ĉӎ����������Ă݂�ƁA���́A�������D���Ȑl�A�����I�Ȑl���ނ���l�b�g�V���b�s���O�����Ă���B��ʍs��������ƁA�����Ԃł��낢��ȂƂ���ɍs���Ă���l�̂ق����l�b�g�V���b�s���O�����Ă���B���C�Ȑl�͉�������ɂ��Ă����C�Ȃ�ł��ˁB�ǂ������������\��������悤�Ȃ��Ƃ��킩���Ă����B �@�ł͂��������l�������A�ǂ�����Ă�����x�܂��̂Ȃ��Ɉ����߂��̂��B���Ƃ��z�[���y�[�W��PR�̎d���Ƃ��A�����������̂�ς����ق���������Ȃ����Ƃ������Ƃ���N�x���b�������Ă��������܂����B |
|---|
�y�n�Q�n���́z
|
|
�@��������͂����������̐�̘b�ŁA�V�����b�ɂȂ�܂��B �@O2O���͂Ƃ����͉̂��̂��Ƃ��B���t�I�ɂ��܂�m���Ă��Ȃ���������܂��A����́uOnline to Offline�v�Ƃ����p��ł��B������ȗ����Ă��̕���ł́uO2O�v�ƌ����Ă��܂��BOnline�Ƃ����̂̓l�b�g��ł��B�Q�Ƃ����̂́A�p��́uto�v�𐔎��̂Q�ɒu�������������ŁAOffline�Ƃ����̂̓l�b�g���g��Ȃ��Ƃ������Ƃł��̂ŁA�l�b�g�ɂ���l����������Ȃ��Ɏ����Ă���Ƃ����̂��A����O2O�Ƃ����l�����ł��B |
|---|
�����̃V���b�v�T�C�g���ݒn�F�i�i��j���ЁE�G���j
|
�@����������̃f�[�^�ł����A�V���b�v�T�C�g�����n���������Ƃ��ɁA���{�̂Ȃ��ɃI�����C���̍s���悪����̂��ɂ��āA�ǂ������Ă݂܂����B �@���݂͂�������Ă��Ȃ��̂ł����AGoogle���z�[���y�[�W�ɁuPageRank�v�Ƃ��������L���O��t���Ă��܂����B�A�N�Z�X����₷���悤�ȂƂ���̓y�[�W�����N�������Ƃ����]��������Ă��āA���ꂪ�V���b�v�T�C�g�Ƃ��Ăǂ��ɂ��邩��ǐՂł��܂����B���Ƃ��Ζ{������A�{��G���Ȃǂ��Ƃ��̃V���b�v�T�C�g�́A�����̂���ǂ̂悤�ȂƂ���ɂ��������Ƃ����ƁA�����̐ԐF�̂Ƃ���ł��B�������ӂ�59�T�C�g�������킯�ł��B70�p�[�Z���g�̃V���b�v�T�C�g�����ǂ͓����ɏW�����Ă����B �@�k�C���́A�D�y�ƈ���ɂ͂���܂����A�L���ɂ͂Ȃ��A���ɂ��Ȃ��A���k�A�l���ɂ��Ȃ��ȂǁA���̂�����������ɏW���̏�����킯�ł��B |
|---|
���͌��ʁi�V���b�v�T�C�g���ݒn���́F���ЁE�G���j
|
�@���������ڂ����A�~�N���Ɍ���Ƃ����Ȃ��Ă��܂��B�����ł��A���c��A������A�V�h��ł��ˁB�_�c�̏o�ŊX�Ȃǂɂ���������T�C�g������܂����A�����̂Ȃ��ł����������Ƃ���Ɉ��|�I�ɏW�����Ă��܂��B �@����ŁA�L���ɂ͂Ȃ��̂ɒ����n���̒��挧�̎R�̒���A�啪���̓��z�@�Ȃǂɂ���̂ł��B����̓T�C�o�[�X�y�[�X�����ʼnc�Ƃ��Ă���悤�ȂƂ��낪������������킯�ł��B�ʏ�ł͍l�����Ȃ��ƒn�ɂ��������T�C�g���������肷��B���Ђ𑗕t����q�ɂ��������Ă����肷��̂ł��B�悤����ɒn���s�s�̕��ʂ̂܂��ł͂Ȃ��āA�{���ɓ����̏����g���A���ꂩ�A���܂܂ł܂��ƔF������Ă��Ȃ��悤�ȂƂ��납�A�ǂ��炩�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ������܂��B |
|---|
���p�������܂��͗��p���Ȃ��Ȃ����X�܂̗��n�������Ƃɂ݂����p�����̔������p�x�i��錧�����Z�ґΏہA�����j
|
�@���ۂ̂܂��Ȃ��ŁA�ǂ�ȂƂ��낪�H��ꂽ�̂��B������ǂ��������ق��������Ƃ������ƂŁA����͈�錧�̃l�b�g���g���Ă���l�Ƀl�b�g�������������ʂł��B�u�l�b�g�Ŕ��������̂́A�{���ǂ��Ŕ����Ă��܂������v�Ƃ�����������܂����B����ƁA��^�V���b�s���O�Z���^�[�̓X�܂Ƃ��A�������������̓X�Ŕ����Ă����悤�Ȃ��̂��Ă���B������ŏ��̗\�z�ƈႤ�̂́A�u���S�s�X�n�����ނ��Ă���B���������Ƃ���̂��̂��l�b�g�ɍs���Ă���v�Ƃ����c�_��������������܂����A�����ł͂���܂���B���S�s�X�n�Ŕ����Ă�����̂͋����͂��Ȃ��̂ŁA�x�O�^�̃V���b�s���O�Z���^�[�ȂǂŔ����Ă�����̂��A���̓l�b�g�Ƌ������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B |
|---|
�l�̓��������傫���ς����
|
�@����͂��̑O���\�����S���p�[�\���g���b�v�����̌��ʂł��B�����������Ƃƍ��킹�āA�l�̓������̂��A������x���邢�낢��ȏ������傫���ς���Ă��Ă��܂��B������Z�b�g�ōl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����͒j���Œn���s�s���ɏZ��ł���l�̌��ʂł��B�S���p�[�\���g���b�v�����͏��a62�N���炸���ƌp�����Ă��āA����͕���27�N�A�ŐV�̃f�[�^�ł��B�S����70�s�s���炢�̃f�[�^�����p���I�ɂƂ��̂�40�s�s���炢�ł����A���̂�����{�I�ȃp�[�\���g���b�v�̏�ǂ������Ă��܂��B �@�������̐����A�S��ʎ�i�ł̂P���̐������P�ʂł��B���Ă݂܂��ƁA���Ă͎Ⴂ�l���������������Ă����̂ɁA20�Αオ�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B����҂��������������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B �@����ɁA���ꂪ�Ռ��I�ł����A�����Ԃɂ��g���b�v�������P�ʂ́A70�Α�ȏ�̂Ƃ���͂������������āA30�Α��艺�͒Ⴍ�Ȃ��Ă���B�����Ԃ͍���҂̌�ʎ�i�ɂȂ��Ă��āA�Ⴂ�l�̌�ʎ�i�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B����͔N��I�Ȃ��̂��������������Ă��Ă���Ƃ������Ƃ������܂��B |
|---|
�^�E���R���V���X�ȃl�b�g���l�b�g�R���V���X�ȃ^�E���̏d�v��
|
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���āAO2O�Ƃ��Ăǂ����ǂ����玝���Ă������B���́u�|�P����GO�v�Ƃ����̂�O2O�ł��B�悤����ɁA�I�����C���łȂ������܂܂ł����A�܂��Ȃ��ɐl��A��o�����Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B �@�T�C�o�[�X�y�[�X�ƃ��A���X�y�[�X�Ƃ����܂��g�ݍ��킹�Ăǂ�����Ă������Ƃ������Ƃ��A��͂肱�ꂩ��͐헪�I�ɋ��߂���Ƃ������Ƃł��B |
|---|
�{�݁E�X�܂ւ̗��K�𑣂��L��Ɋւ���Web�A���P�[�g����
|
�@���ۂɎ���Ԃł��X�������Ă���y�V���T�[�`�̉���̕��ɁA�uO2O�Ƃ��āA�l�b�g�ōL�����ēX�Ɏ��ۂɗ��Ă��炤�헪�Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȑ헪���̂��Ă��܂����v�Ƃ����������s���܂����B �@�ǂ̂悤�Ȃ��X�ɑ��Ē����������Ƃ����ƁANAVITIME�̌����z�b�g�X�|�b�g�̃����L���O��ʂ̏W�q�͂̂���{�݂̕��ɂ��u�˂��܂����B�ǂ̂悤�ȗ��R�ł��q���������Ă��邩������ƁA�������������I�ł��B |
|---|
����Ԃւ̗��X�E���K�𑣂��{��
|
|
�@�u���ӂ̃C�x���g�̏Љ�v�������ӂ̃C�x���g���l�b�g�ŏЉ�Ă�����A����I�ɂ��낢��Ȃ��Ƃ���������ł���Ƃ���̂ق����A���q������Ԃł����Ă���Ă��܂��B |
|---|
���X�E���K�҂̑����v��
|
�@���������ӊO�������̂́A���ʐς��傫�����X��l�b�g��Ŕ̔����������Ă���悤�Ȃ��X�̂ق����A���ǂ͎���Ԃɂ��������Ă����Ƃ������Ƃł��B������A�����Ă���Ƃ���͗����ŏ����Ă���킯�ł��ˁB���������\���������Ă��Ă���ƌ����܂��B |
|---|
�y�`�F�b�N�C���X�|�b�g����s�s������z�@�e��SNS�̓����Ɨ��p��
|
�@�����A�`�F�b�N�C���X�|�b�g����s�s������Ƃ������Ƃł��B�`�F�b�N�C���X�|�b�g�Ƃ͉��̂��Ƃ��A�Ⴂ���͒m���Ă���l�����������킩��܂��A�v�����SNS�ł��BSNS�̕��͂�������Ƃ��Ă݂悤�Ƃ������Ƃł��B���܂��܂�SNS������܂����AFacebook��Twitter�̕��͂����Ă��܂��B���[�U�[�̐������ɑ������̂Ɋւ��ĕ��͂����Ă��܂��B |
|---|
�`�F�b�N�C���X�|�b�g(����ԂƃT�C�o�[��Ԃ̌�M�ꏊ�j�ւ̒���
|
�@Facebook�͑S���E�̃A�N�e�B�u���[�U�[��20���l�Ƃ������Ƃł��B����Facebook�𗘗p���Ă���l��33.7�����`�F�b�N�C���Ƃ������̂𗘗p���Ă��܂��B�`�F�b�N�C���Ƃ����̂̓z�e���̃`�F�b�N�C���ł͂Ȃ��āA�܂��Ȃ��ŁA�����͋C�ɓ������Ƃ����Ƃ���ɂ��āA�u����͂����ɗ������v�Ƃ������Ƃ����̏ꏊ�ɍ���s�ׂł��B����Łu�������悩�����v�Ƃ����悤�ȃR�����g�𓊍e���܂��B�Ƃ������Ƃ́A����������ԂƃT�C�o�[��Ԃ̐ړ_�ɂȂ��Ă���킯�ł��B �@����͂�������O2O���ʂ�����܂��B�`�F�b�N�C���{���҂̂V�����A�`�F�b�N�C���̉{�������������ŁA���̏ꏊ�ɗ��Ă���B�ł�����l�b�g�̂Ȃ���Łu������������v�ƌ�����Ƒ��̐l������B�l��ނ��Ă��܂���ł��ˁB�����������ʂ�������̂ł��B |
|---|
�g�p�f�[�^�T�v
|
�@������������S��PT�����Ă���s�s�ŁAFacebook�̃`�F�b�N�C���E�����L���O�̊e�s�s�̏��100�X�|�b�g�����ۂɌ��āA2013�N��2016�N�̂Q���_�̃f�[�^���r���Ă��܂��B���̃f�[�^�͗ݐσf�[�^�Ȃ̂ŁA�ŏ��ɒN�����`�F�b�N�C�������Ƃ�����A�����Ƃ��̐����������Ă����܂��B�ł�����2013�N�̃f�[�^�͂��̂Ƃ�����Ă��Ȃ��Ƃ����킩��Ȃ��Ƃ������̂ł��B2016�N�͍�N���܂����B |
|---|
�D�y�ɂ�����`�F�b�N�C���X�|�b�g�ω��̎���
|
�@���Ƃ��ΎD�y�s������ƁA���F���Ƃ���͎D�y�s�����_�ɂ������ƌ����Ă��镔���ŁA�Ԃ����������ۂɃ`�F�b�N�C������Ă���Ƃ���ł��B��������ƁA�D�y�h�[�����ʌ����Ȃǂ��`�F�b�N�C���̏�ʂɗ��Ă���킯�ł����A�N�ɂ���ĕϓ������낢�댩���܂��B�D�y�̏ꍇ������ƁA�`�F�b�N�C������Ă���Ƃ��낪�܂��̐^�ɂ�����Ƃ���킯�ł��B����͂��Ƃ��Η��n�K�����ŃR���p�N�g�Ȃ܂��Â�������܂��傤�ƌ������Ƃ��ɁA����ԂŃC���[�W���Ă�����̂ƃT�C�o�[��ԂŃC���[�W����Ă�����̂Ƃ��A���Ȃ�d�Ȃ��Ă��Ă���Ɨ����ł��邩�Ǝv���܂��B |
|---|
�t����ɂ�����`�F�b�N�C���X�|�b�g�ω��̎���
|
�@����ŁA�܂������t�̂܂����Љ�Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B�t����s�͂��̉��F�̕��������_�Ƃ��Ă܂��̏W�ς�}��Ƃ����v���������킯�ł����A����Ƃ͂���W���Ȃ��Ƃ��낪�`�F�b�N�C������Ă���Ƃ����ɂȂ��Ă��܂��B �@�����ƃ`�F�b�N�C���s�ׂ������Ă����ɐl����������悤�ɂȂ����ꍇ�ɁA����Ԃ̌�ʍs���Ƃǂ̂悤�Ȑ��������Ƃ�̂��Ƃ������Ƃ���̉ۑ�ɂȂ�܂��B |
|---|
�`�F�b�N�C��������ȓs�s�̔c��
|
�@2013�N��2016�N�ƂŁA�`�F�b�N�C���̔䗦�����Ă��܂��B���ۂ�2016�N�ɂǂꂾ���`�F�b�N�C������Ă��邩������ƁA�E���オ��̏ɂȂ��Ă��܂��B��s�s�͓��R��ɗ���킯�ł����A2013�N����2016�N�̂R�N�Ԃ����Ń`�F�b�N�C���̐���10�{�ȏ㑝���Ă�����̂��������������B������݂�ȃl�b�g�ˑ��̂������ɂ����������Ă���B �@���Ƃ́A�s�s���̋K�͂ł��Ȃ�p�^�[��������Ă��܂��B�������s�s�́A�����Ƀ`�F�b�N�C���̐��������Ă��܂��B�����Ȃǂ͔��p�قł��Ȃ�҂��ł��܂��B���ߎw��s�s�Ȃǂ́A�`�F�b�N�C���̑����͑傫���̂ł����A�}�ɑ�������͂��Ă��܂���B |
|---|
�`�F�b�N�C��������ȃX�|�b�g�̔c��
|
�@����͉�A���͂����āA���������Ă��邩�����Ă��܂��B��N�l���䗦������������A���͓x���傫���s�s�́A��͂�`�F�b�N�C���������B���Z�҂��悭���p����悤�Ȏ{�݁A�悤����ɍL��Ƃ������A��Î{�݂Ȃǂɂ͊�{�I�ɂ̓`�F�b�N�C�����Ȃ��킯�ł��B��͂�ό��{�݂̃`�F�b�N�C���������B |
|---|
�����K�Ґ��Ɍ���`�F�b�N�C���X�|�b�g�̈ʒu�Â�
|
�@����͊w���ɂ��Ă�������̂ł����A�`�F�b�N�C���̗ݐωƁA���ۂɂ��̎���Ԃɉ��l���Ă��邩�Ƃ������ւ�����ƁA��͂肠����x�̑��֊W�������Ă��܂��B�����C�݁A�֒�M�C�A�F�{��A�����h�[���A���Z���ȂǁA���̂悤�ȊW�ɂȂ��Ă��܂��B |
|---|
SNS�ŏ�M����₷���ꏊ�̓����c��
|
�@�ό�������������Ƃ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B��͂菼���C�݁A�֒�M�C�Ȃǂ́A�������ƍ���҂��s���Ƃ���ł��ˁB���Ƃ͖��É���A�F�{��Ȃǂ̂����|�[�g�^���[�A���É��e���r���A��t�|�[�g�^���[�ȂǁA�悤����Ƀ����h�}�[�N�I�Ȃ��̂̃`�F�b�N�C���̐����A���ΓI�ɖK���l���������킯�ł��B�ł�����A�v��I�ɂ������ǂ����킩��܂��A�ڗ����̂�Ƃ����Ń`�F�b�N�C�����Ă����Ƃ����X��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B |
|---|
�y�c�C�[�g�����s�s�z�@�g�p�f�[�^�̊T�v����ёΏۓs�s
|
�@�c�C�[�g�̒��g�Ɋւ��Ă��s�s�Ƃ̊W�������Ȃ����Ƃ������ƂׂĂ��܂��BTwitter�͓�����������܂��̂ŁA�l�ԊW���C�ɂ��Ȃ��ŏ������߂܂��B���Ƃ͊g�U��������܂��B�����œ���̓s�s�����܂ރc�C�[�g��N�������w�肵�Č��o���āA���̓s�s���Ƃǂ�Ȍ��t���Z�b�g�Ō�������Ă��邩�͂��܂����B |
|---|
�s�s�ɂ��c�C�[�g���̑���
|
�@�Ƃ肠�����A�������L�����N�^�[�̈Ⴄ�s�s�ɂ��āA�X���̕�����14����ɂ�����c�C�[�g���ׂ܂����B������͑ΐ��\���Ȃ̂ŁA���ۂɂ͂��̂�������������܂��B�s�s�ɂ���āA�c�C�[�g�łԂ₩��Ă��鐔�Ƃ����̂́A�l���̔�Ȃǂɂ���ׂĂ��傫�ȍ�������킯�ł��B���R�A����D�y�Ȃǂ̑傫���s�s�͂�������Ԃ₩��Ă���킯�ł����A�����Ƃ��V���Ȃǂ́A���̎��ԑт͒N�����͂Ԃ₢�Ă��Ȃ��B�܂��A�y���Ȃǂ̊ό��n�͂��������Ԃ₩��Ă��܂��B�ꏊ�ɂ���ĂԂ₫�̓x�������܂������Ⴄ���Ƃ������Ă��܂��B |
|---|
�������̍\���v�f�̔c��
|
�@��A���͂����āA�ǂ�Ȃ��Ƃ��e�����Ă��邩������ƁA���ۂɃC�x���g��łƁA�����������ɔ�������̂ł��B�C�x���g��G�߁A�l���▣�͓x�Ȃǂ��W���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B |
|---|
�s�s�ɂ��c�C�[�g���e�̑���
|
�@���ꂼ�ꓯ�����ԑт����Ă��A�܂��ɂ���ĂԂ₩��Ă��邱�Ƃ͂܂������Ⴂ�܂��B�D�y�́u�h�[���v�Ƃ��u�`�P�b�g�v�A�u���[�����v�Ȃǂ��Ԃ₩��Ă��܂��B��ł͎s���I�������āA�u�s���v��u�ېV�v�Ƃ������t���o�Ă���B���͌��̓��j�A�̘b������̂Łu���j�A�v����ʂɏo�Ă��Ă���B�܂������s�s�̃L�����N�^�[���Ⴄ���A��͂藬���I�Ȑ��i�����ɋ����Ƃ������Ƃł��B |
|---|
�X�̃L�[���[�h�Ɍ��闬�����̓���
|
�@���ԑт�G�߂ȂǂŌ���ƁA�D�y���ǂ������܂��Ȃ̂��Ƃ����ƁA�u�h�[���v��u�c�A�[�v�A�u���C�u�v�Ȃǂ���������o�Ă���킯�ł��B�ł�����D�y�Ƃ����̂͂��������L�����N�^�[�Ȃ̂��Ǝv���܂����A������A���Ƃ��u�f���w���v��u�����v�A�u�l�ȁv�Ƃ������̂��o�Ă��āA�D�y�̗��̊炪�킩���Ă��܂��Ƃ������Ƃ�����܂��B���Ƃ́A�~�ł��Ăł���ɂȂ�ƃ��[��������ʂɗ��܂��B �@����������������ȂƎv���܂����A�s�s�̎��ۂ��ǂ��Ȃ��Ă���̂�������Ƃ��ɁA�݂Ȃ����ʂɎg���Ă��錾�t�����������Ӗ��������Ă���Ƃ������A�^�����킩����ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B |
|---|
�s�s�̏��ς��
|
�@����܂ł͋�������ǂ������̂ł����A�l�b�g�ɂȂ�ƌ��ꂪ�o���A�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA���ꌗ���Ƃɂǂ̂悤�ȓs�s�������c�邩�ɂ��āA����͐̍�����f�[�^�ł����A���ۂɃy�[�W�����N�̒l�����Ȃ��璲�ׂ����̂ł��B |
|---|
�V���b�v�T�C�g�������@
|
�@69������Google�I�����C���V���b�s���O�̂����܂̌���ɂ��āAPageRank�̍����V���b�v�T�C�g��T���܂����BPageRank���̂�2016�N�ɔp�~����Ă��܂��B |
|---|
���͌��ʁ|�t�����X�ꌗ
|
�@���Ƃ��t�����X����g���Ă���Ƃ���ł��ƁA�p���Ɉ��|�I�ɃT�C�g���W�����Ă���Ƃ������Ƃ�����܂��B |
|---|
���͌��ʁ|�p�ꌗ
|
�@�p�ꌗ�̏ꍇ�́A�C���h��J�i�_�A�I�[�X�g�����A���p�ꌗ�Ȃ̂ŁA���̂悤�ȃG���A���p��̃T�C�g�Ƃ��Ă͋�������Ƃ���ɂȂ�܂��B�l����Ō���ƃC���h�������킯�ł����A�T�C�g�������Ō���ƃA�����J�����|�I�ɍ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�A�����J�̂Ȃ��ł����낢����Ă��܂��B |
|---|
���͌��ʁ|�h�C�c�ꌗ
|
�@�h�C�c�͂������ϓ��ł��B���ۂ̓s�s�̐l���K�͕��z���ϓ������A���܂�T�C�g�̕���Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂��B |
|---|
���͌��ʁ|�X�y�C���ꌗ
|
�@�X�y�C���ꌗ�͂��傤�ǓƗ��̘b�����Ă��ē����I�ł����A�}�h���[�h�ƃo���Z���i����͂苭�����Ƃ��킩��܂��B |
|---|
���͌��ʁF�s�s�K�͍\���̔�r�i1�j
|
�@�����N�T�C�Y���[���Ƃ������ƂŁA�s�s���ʂƐl���̏��ʂ��Ƃ�ƁA���{�͈�ɏW���ł��B�^�̐���ɂ̂�ƈ�ʓI�Ƀ����N�T�C�Y�̏��ʂ��ϓ��ɉ������Ă����̂ł����A���̃��C���ɂ̂�ƈ�ɏW�����������i��ł���Ƃ������Ƃł��B��̃��C���ɂ̂�ƕ��U�^�ł��B���{�̏ꍇ�́A�l���͓�����ɏW���ƌ����Ȃ��炯�������ϓ�������ǂ��A�T�C�g�Ō���ƈ��|�I�ɓ������������Ƃ��킩��܂��B |
|---|
���͌��ʁF�s�s�K�͍\���̔�r�i2�j
|
�@���̍������Ă����ƁA�A�����J�͐l�����T�C�g�����ϓ��ł����A�t�����X�͐�قnj������悤�ɐl���������Ȃ��ɏW���ɂȂ��Ă��܂��B |
|---|
���͌��ʁF�s�s�K�͍\���̔�r�i3�j
|
�@�h�C�c�͕��U�^�ł��B�X�y�C���̓}�h���[�h�ƃo���Z���i�����������āA���Ƃ͂���قNj����Ȃ��Ƃ������Ƃ��T�C�g���ł̌X���ł��B |
|---|
�l�@�F���ꌗ
|
�@���܂̓s�s�̏W���╪�U�̌X���́A�l�b�g�̐��E�ɂȂ�Ƃ�苭���Ȃ�X���ɂ���B���U���Ă���Ƃ���͂�蕪�U���邵�A�W�����Ă���Ƃ���͂��W������Ƃ����X�����o�Ă��������Ǝv���Ă��܂��B |
|---|
�v���o�����Ƅ�����䶗��ƃG���g���s�[
|
�@�݂Ȃ���̂��苖�ɂȂ��������P�����������āA����ɂ��čŌ�ɂ��b���������Ǝv���܂��B������̓G���g���s�[�̎��ŁA�����炪��䶗��ł��B�����؍j�搶���G���g���s�[�@������Ă����̂͂悭���������Ǝv���܂����A�������������傳���Ă��������悤�ɂȂ�������͌F��ɘA��Ă����Ă����������肵�āA��䶗��̂��b�������ԕ������Ă��������܂����B |
|---|
��������
|
|
�@�����炭1989�N�̏H���Ǝv���܂����A���͏���̂P�N�ڂŁA�{���ɉ����������Ă������悭�킩��Ȃ��A������������̂��Ƃł��B�����ؐ搶��1931�N�̂����܂�Ȃ̂ŁA���̂Ƃ���58���炢�������Ǝv���܂��B���s��w�̌������͂��܂肢������Ɉ��݉�����邱�Ƃ��Ȃ��̂ł����A�����炭���c���F�搶�����Ă���āA�v��n�����̍��e��̐Ȃ�݂��܂����B���̐Ȃō����ؐ搶������ꂽ���Ƃ��A���͂�������ۂɎc���Ă��܂��B �@����́A�����ؐ搶���������N��̐搶�ɑ��āA�����ؐ搶�������������݂����̂ł��B�ǂ��������Ƃ����݂��ꂽ���Ƃ����ƁA���̔N��̐搶���G���g���s�[�@�I�Ȑ��w���K���K���g���悤�Ȍ���������Ă������Ƃɑ��āA�����������Ƃ�����ꂽ�̂ł��B�u������x�̔N����߂�����A�����҂Ƃ��Ă̍⓹���ǂ�����̂��A������l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��傤�v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂����B �@�l���Ă݂�ƁA���͂���56�Ȃ�ł��ˁB���̂Ƃ��̍����ؐ搶�ƂQ�������Ȃ��̂��Ǝv���Ɗ��S�[�����̂�����܂��B�オ�����Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł����A���������鏀�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��ȂƎv���Ă��܂��B���̈Ӗ��ł́A���̏܂��������������Ƃ��_�@�ɁA������x�n���܂��l��邮�炢�̂��Ƃ������������ȂƎv���Ă��܂��B�����錾���Ď����Ƀv���b�V���[�������āA���傤�ǎ��Ԃł��̂Ŕ��\���I��点�Ă������������Ǝv���܂��B�����͂ǂ������肪�Ƃ��������܂����B |
|---|