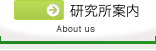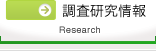ホーム>公益事業情報>米谷・佐佐木基金>過去の授賞式>第7回米谷・佐佐木基金> 受賞者(学位論文部門)の挨拶と受賞講演
米谷・佐佐木基金
受賞者(学位論文部門)の挨拶と受賞講演
 |
桑野 将司 【 研究題目 】 本日は、大変名誉ある賞を授与いただきまして誠にありがとうございます。 本学位論文は広島大学で提出しました。広島大学の先生方をはじめ多くの方々にご支援とご指導を賜りました。この場をお借りして厚く御礼申しあげます。 それでは、私の学位論文の内容について、ごく簡単にご紹介させていただきます。 |
|---|
1.背景と目的
|
(自動車普及と生活様式の多様化) 我が国では1960年代に自動車の普及が始まり、自動車の保有台数、利用距離は増加の一途を辿ってきました。 このようなモータリゼーションの進展によるモビリティの向上は、好きな時に好きな場所に行ける、つまり各個人がもつ価値観をそのまま交通行動に反映させることが可能となり、結果として我々分析者が観測できる交通行動の多様化につながっていると考えています。 一方で、モータリゼーションの進展は、さまざまな交通問題を引き起こしています。その一つに環境問題があり、自動車から排出される二酸化炭素の削減は政府の最重要課題の一つとして挙げられています。 |
|---|---|
 |
(二酸化炭素削減政策に関する課題) これらの問題を解決するために、国内外で多くの研究がなされていますが、いくつか問題点が残されています。 一つ目が、既往研究の多くが、需要が集中する都市圏を対象に研究を行っており、地方圏を対象とした研究が比較的少ないのです。地方圏では自動車交通を前提とした都市形態あるいは生活スタイルになっており、都市圏で有効な政策が必ずしも地方圏でも有効だとは限りません。 また、二つ目の問題点として、自動車の保有・利用行動は、複数の行動段階で構成されていますが、それらを総合的に分析できる分析手法は開発されておらず、ある政策の実施が世帯行動にどのように影響を及ぼすかを評価されているとは言い難いと思っています。 さらに、既往研究の多くは世帯の意思決定における同質性を仮定し、平均的な自動車利用行動を前提とした分析が行われており、世帯行動の多様性が充分に考慮されていません。 |
 |
(研究の目的) 本研究では、これらの三つの課題点にとくに着目し、地方圏を対象として、世帯行動の多様性の考慮と購入から廃棄に至るまでの一連の行動を総合的に取り扱うことができる統合型のモデルを開発することによって、世帯の自動車保有・利用行動メカニズムの解明を目的に研究を行いました。 |
2.研究のねらい
|
(本研究での"多様性"の定義) タイトルにもあります多様性について、本研究の考え方をご説明します。どのような車がほしいかとか、どのように車を使いたいかというような意思決定の最小単位は個人であります。その価値観が異なる異質な個人の集団として世帯は構成されています。 ここで、世帯に属する個人は家計を共有しているということ、また買い物や送迎など他の構成員のための自動車利用が存在するという点で、自動車の保有・利用行動は個人の意思決定ではなく、世帯としての意思決定だと考えています。 ここで、選好や世帯内で役割が異なる異質な個人が共存する集団としての世帯の意思決定メカニズムが世帯間で異なること、これを本研究では「世帯行動の多様性」と呼んでいます。そして、同じような個人に同じ政策を実施したとしても、世帯という集団を介することによって世帯として現出する行動に違いが見られること、これを本研究では「政策反応の多様性」と呼んでいます。 これら世帯行動あるいは政策反応の多様性を、本研究では考慮していきます。 |
|---|---|
 |
(世帯行動の多様性の考慮した分析方法) 具体的な多様性を考慮した分析手法としては、サンプルを同質なグループに事前にセグメントする方法とモデルのなかで内生的にセグメントする方法との二つが考えられます。本研究では後者の、内生的にサンプルをセグメントしていく潜在クラス手法を適用しています。 潜在クラスとは、直接観測できない要因によって分類された同質なグループのことを意味しています。潜在クラス手法の適用によって、各潜在クラス、同質なグループへの帰属確率と帰属要因が明らかとなり、分析結果の解釈が容易であるという点、また対象者を絞った的確な政策検討ができるという点で、潜在クラス手法の利点がございます。 |
 |
(統合型モデルの必要性) 続いて、もう一つの本研究の柱である統合モデルの必要性についてご説明します。 たとえば、ガソリン代が高くなったから、予定していたよりも早い段階で燃費のいいハイブリッド・カーに乗り換えるというように、ある段階の行動変化は、他の段階での行動変化を連鎖的に引き起こすと考えられます。 従って、一つの段階にのみ着目した政策評価は、他の段階の行動変化を考慮していないため、政策の効果を過大あるいは過少に評価する危険性があり、本研究ではこれらを総合的に取り扱うことができる統合型モデルの開発を行いました。 |
 |
(各段階を構成する行動要素) さらに、購入、保有、走行段階は、複数の行動要素で構成されています。たとえば購入段階は、どのような車を買うかという車種選択と、何台車をもつかという保有台数選択に分類できます。 ただし、近年自動車の保有台数には大きな変化がなく、飽和状態にあると言われています。これはすでに各世帯が必要なだけ自動車が行き渡っていると考えて、本研究では保有台数選択は取り扱わず、どのような車を選ぶかという車種選択についてのみ離散選択モデルで分析します。 残る走行段階、保有段階は、購入段階にくらべてより多くの行動要素で構成されています。これら一つひとつの行動要素についても車種選択と同じように離散選択モデルを用いて分析することも可能ですが、そうすると調査票やモデルの複雑化を避けることができません。そこで本研究では、走行段階と保有段階については日常の選択の時間的な集計値である年間走行距離と保有期間に着目し、これらを統計記述モデルを用いて分析しています。 |
 |
(統合型モデルの枠組みと分析の流れ) 本研究の流れは、まず各段階を構成するサブ・モデルを構築したのち、最後にこれら三つの段階を同時に取り扱うことができる統合型モデルへと展開しています。 |
3.世帯モデルの開発
|
(車種選択モデルの課題) ここからサブ・モデルの内容について簡単にご紹介します。 一つ目のサブ・モデルが、車種選択を対象にしたモデルです。車種選択は、個人が単独で行っているのではなく、世帯としての意思決定であると考えています。そこで世帯意思決定モデルの適用が必要になるのですが、既往研究において既に加法型モデル、妥協型モデル、独裁型モデルという複数の世帯意思決定ルールというものが提案されています。 また同時に、世帯はその構成員、意思決定の対象、世帯内での権力構造などの文脈によって採用する意思決定ルールが変化することも指摘されています。すなわち、分析者にとってどの意思決定の文脈においてどの意思決定ルールが支配的であるかを事前に把握することは困難です。そこで本研究では、意思決定ルールを事前に仮定するのではなく、モデルのなかで内生的に決めることができる複数の世帯意思決定ルールを同時に取り入れた世帯離散選択モデルの開発を行っています。そして、それを車種選択行動に適用しました。 |
|---|---|
 |
(世帯意思決定モデル) 具体的には、先ほどの潜在クラス手法を適用しています。この潜在クラス手法を適用することによって、サンプルのなかにいくつの同質なグループが存在するか、つまり潜在クラスの数がいくつか。そして潜在クラスごとの意思決定ルールとそのときの効用関数のパラメータ、また各世帯がどの潜在クラスに帰属するかとそのときの帰属要因をすべて同時にモデルのなかで推定することができます。 この潜在クラス手法による複数の世帯意思決定ルールを中国地方で収集したデータにあてはめて、実証分析を行いました。 |
 |
(世帯車種選択モデルの推定結果) 分析の結果、今回私が取得したデータにおいては、二つの潜在クラスが抽出されました。そして、帰属要因に関するパラメータの推定結果から、中高年世帯は潜在クラス1に、若年世帯は潜在クラス2に属する割合が高い。また、それぞれ車種の選択確率と価格に対する反応が異なることがわかりました。 これらの結果は、ライフ・サイクル・ステージの違いによって各世帯が従う意思決定ルールや車種選好の割合、価格に対する感度は異なるということを意味しています。 続いて走行段階と保有段階のモデル化についてご説明します。 |
4.同時決定モデルの開発
|
(走行段階と保有段階の関係) ここでは、既往研究の多くが走行段階、保有段階のそれぞれ別々に分析を行っているのに対し、本研究ではこれらの相互依存性を考慮したかたちで同時決定モデルとして定式化している点に特徴があります。 |
|---|---|
 |
(多変量生存時間モデル) 具体的には、保有期間と年間走行距離の2変量を目的変数とした2変量生存時間モデルを開発しています。これによって、保有期間と年間走行距離のそれぞれの分布およびそれに影響を与える要因、またこれらの相互依存性を同時に分析することができます。 |
 |
(コピュラ関数) この2変量生存時間モデルの解法として、新たにコピュラ関数を導入しました。コピュラ関数とは、周辺分布間の依存構造を決定し、多変量分布を表現するための関数です。この関数は、定義式によって多様な依存構造を少ないパラメータで表現できるという特徴がございます。 |
 |
(同時決定モデルの有効性の確認) このモデルを用いて先ほどと同じデータで実証分析を行ったところ、従来の相互依存性を考慮していない独立モデルにくらべて、本提案手法のほうがモデルの適用度、現況再現性ともに高いことがわかりました。 これらの結果から本提案手法が有効であることがわかりましたので、さらに多様性を考慮するために、潜在クラスを追加的に導入しています。 |
 |
(多様性を考慮した同時決定モデルの推定結果) 保有期間、年間走行距離を対象にした潜在クラス・モデルを推定したところ、ここでもやはり二つの潜在クラスが抽出されました。また、帰属確率に関する説明変数から、潜在クラス1には若年世帯が、潜在クラス2は中高年世帯が属しやすいことがわかりました。 すなわち、車種選択と同様に、自動車の保有期間あるいは年間走行距離においても、ライフ・サイクル・ステージが行動に有為な差を与える重要な要因であることを意味しています。 |
5.統合型モデルの開発 - 提案モデル・システムの枠組み
|
以上の二つのサブ・モデルを踏まえて、最後に統合型モデルを開発しています。 ここでは、先ほど構築した二つのサブ・モデルの説明変数を共有化する、あるいは片方のサブ・モデルのアウトプットをもう片方のモデルのインプットに用いることにより、三つの行動を結合しています。 |
|---|
6.政策分析 - シミュレーション分析の結果
|
そして、構築した統合モデルを用いて、購入費用、走行費用、保有費用の各段階における費用変化をシナリオとして与えたシミュレーション分析を行っています。 これによって、ある段階での費用変化──たとえば購入費用の変化が車種選好に及ぼす影響だけではなく、年間走行距離や保有期間にどのように影響を及ぼすかの分析が可能となり、これらの結果として算出される二酸化炭素排出量がどのように変化するかの分析ができます。 これによって、どの段階でどれぐらい費用を変化させればCO2削減にどの程度寄与できるかの分析が可能となっています。 |
|---|
7.結論
|
(本研究のまとめ) 以上、本研究の成果をまとめます。本研究では、多様性を取り入れた分析手法と統合型の自動車保有・利用行動分析手法の開発を行いました。 |
|---|---|
 |
(本研究の成果) 分析の結果、世帯行動の多様性は世帯のライフ・サイクル・ステージと密接に関係していることがわかりました。また、費用政策については、費用の変化量、変化の期間、変化のタイミングによって世帯の行動が大きく変わることがわかりました。 これらの結果は、今後さらに進行すると予想されている少子・高齢社会において、世帯のライフ・サイクル・ステージの変化と関連づけた政策判断が必要であることを意味しています。よって、将来のライフ・サイクル・ステージの変化を与件とすれば、本提案手法によって世帯の多様な反応が分析可能となり、政策の内容や期間、タイミングに関する有効な政策評価が可能だと考えています。 |
 |
(今後の展開) 最後に今後の展開についでですが、本研究では地方圏を対象にCO2削減政策を検討しました。しかし、地方圏では自動車交通に強く依存しているため、自動車利用を抑制するような政策は、居住者の外出機会や目的地選択の幅を制限し、社会的に容認され難いと思っています。 そこでこれからは、地域の実態に即した地域別の二酸化炭素排出削減ポテンシャルの算出──つまり政府の掲げる国家レベルでの目標値をどのように地域レベルに具現化するかなど、環境負荷とモビリティ水準の維持とを関連づけた研究を行っていきたいと考えています。 また、本研究では世帯内での意思決定を対象に分析を行いましたが、これを友人や知人、近隣住民などを含めたより大きな集団での意思決定に展開することによって、口コミや社会的同調圧力など、人と人とのコミュニケーションを活かした政策の有効性についても検討していきたいと思っています。 以上で私からの発表を終わります。本日は誠にありがとうございました。 |